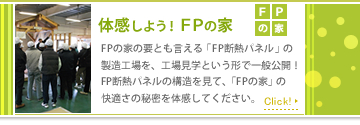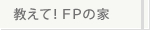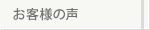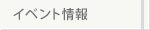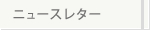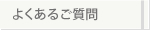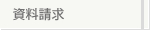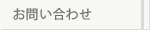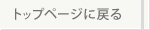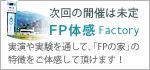青山建設の家づくりプロジェクト!プロジェクト名「ヤナギのエコハウス」です。着工からお引渡しまでの工事状況をリアルタイムでご紹介し、完成してからは見えなくなってしまう部分も全て包み隠さずお見せしています。
2013.05.17
2013.03.28

 防音室が完成しました。工事途中をあまりお見せできなかったのが残念でなりません。部屋に入ったとたん、防音室や音楽室独特のシーンとした空気が漂います。壁は布クロス、天井は吸音板、床は長尺シートですが、いずれの部位にもその裏側に吸音材と防音材が隙間なく入っております。ドアはもちろん防音ドアです。
防音室が完成しました。工事途中をあまりお見せできなかったのが残念でなりません。部屋に入ったとたん、防音室や音楽室独特のシーンとした空気が漂います。壁は布クロス、天井は吸音板、床は長尺シートですが、いずれの部位にもその裏側に吸音材と防音材が隙間なく入っております。ドアはもちろん防音ドアです。2013.03.14
2013.02.28

 ようやく…「HEMS」の設定が出来ました。(汗) これで電気の使用量や太陽光発電量などがパソコン上で表示され、クラウドと呼ばれるところでデータ保管されるそうです。どのくらい省エネとなるのか今から楽しみです!
ようやく…「HEMS」の設定が出来ました。(汗) これで電気の使用量や太陽光発電量などがパソコン上で表示され、クラウドと呼ばれるところでデータ保管されるそうです。どのくらい省エネとなるのか今から楽しみです!2013.02.26
 ウッドデッキを作成しました。まずは2階のバルコニーです。レッドシダーという杉材を、シッケンズという塗料にて塗装してあります。デッキの高さを室内の床とほぼ同じ高さに設定してあるので、気候のいい春や秋はオープンリビングとしても使えます。
ウッドデッキを作成しました。まずは2階のバルコニーです。レッドシダーという杉材を、シッケンズという塗料にて塗装してあります。デッキの高さを室内の床とほぼ同じ高さに設定してあるので、気候のいい春や秋はオープンリビングとしても使えます。デッキは1階にも予定していますので、外構工事と調整しながら製作します。
2013.02.21

 この物件では防音室を作成しています。「大建工業」さんに防音仕様のプランニングをしてもらい、その仕様に沿って施工しています。
この物件では防音室を作成しています。「大建工業」さんに防音仕様のプランニングをしてもらい、その仕様に沿って施工しています。吸音ウールと呼ばれる厚さ5cmの吸音材を壁や天井に埋め込み、石膏ボードを貼り、さらにその上に遮音ボードやシートを貼っていきますが、もちろんジョイント部にも遮音テープやシーリングを施します。結構本格的ですよ!
2013.02.19
 気密測定を行いました。いつも結果が出るまではドキドキします。
気密測定を行いました。いつも結果が出るまではドキドキします。今回は床面積が大きいながらも0.6c㎡/㎡と、「ものすごくいい数値」とは言えませんでした…。一部のサッシから漏気が感じられたので、再度調整してもらい少しでも気密が良くなるようにしたいと思います。
2013.02.14
 2階からロフトへの階段を設置しました。家具屋さんで積層板を加工してもらい、大工さんが現場で組み立てました。箱階段で、下部は飾り棚となっております。
2階からロフトへの階段を設置しました。家具屋さんで積層板を加工してもらい、大工さんが現場で組み立てました。箱階段で、下部は飾り棚となっております。1段1段の寸法を大きく設定しましたが、上り下りがしやすかったです!(笑)
2013.02.12
2013.02.07
2013.02.05
 外構工事も一段落です。植栽が入り、緑化施設の申請と審査も無事完了しました。あとはアプローチや駐車場、ウッドデッキの工事があります。
外構工事も一段落です。植栽が入り、緑化施設の申請と審査も無事完了しました。あとはアプローチや駐車場、ウッドデッキの工事があります。建物も大きかったですが、庭も大きいのでやりがいがあります!ゴールが近づいてきました。完成が待ち遠しい限りです。
2013.01.31

 洗面所の鏡廻りのモザイクタイルを貼りました。色といい形といい、個性豊かなタイルです。貼りたてホヤホヤで目地を込んでいないのでぼんやりしていますが、白い目地を込めば輪郭や色がはっきりと出て、よりきれいになりそうです。完成が待ち遠しい限りです。
洗面所の鏡廻りのモザイクタイルを貼りました。色といい形といい、個性豊かなタイルです。貼りたてホヤホヤで目地を込んでいないのでぼんやりしていますが、白い目地を込めば輪郭や色がはっきりと出て、よりきれいになりそうです。完成が待ち遠しい限りです。2013.01.29

 外構工事が順調に進んでいます。雪が降ったりしてどうなるかと思いきや、一気に植栽が入り庭らしくなってきました。
外構工事が順調に進んでいます。雪が降ったりしてどうなるかと思いきや、一気に植栽が入り庭らしくなってきました。この地域は緑化地域にあたり、敷地が大きいと一定の割合以上の緑を入れなくてはいけません。今回も60平方メートル以上の緑を入れなくてはいけませんので、結構な面積になります…。
今はまださみしい感じですが、春からは色鮮やかな庭になること間違いなしです。
2013.01.24
2013.01.22

 和室のジュラク壁もしっかりと乾燥し、きれいな仕上がりとなりました。やはりクロスとは違った仕上り感です。とってもいい感じです。
和室のジュラク壁もしっかりと乾燥し、きれいな仕上がりとなりました。やはりクロスとは違った仕上り感です。とってもいい感じです。大工さんは洗面所の棚等を取り付けしています。隣の部屋へ洗濯物を移動できるよう、棚の1段分の壁を抜きました。光が漏れていますので、ほんのちょっと明るさも確保できそうです。
2013.01.17
 SII補助金事業の部分の工事は完了し、現在は補助金の申請書類を必死に(笑)作成中です。
SII補助金事業の部分の工事は完了し、現在は補助金の申請書類を必死に(笑)作成中です。現場の方では細かい部分の仕上工事を行っております。もうすぐ畳が入るため、その前に和コーナーにあるキッチンカウンター下の腰壁を貼りました。ちょっと分厚い小巾板を貼りました。
2013.01.15

 クロス工事が順調に進んでいます。ロフト部分のクロスも貼り終わり、玄関正面壁のポイントクロスも貼り分けが終わりました。このポイントクロスは使い方を間違えると失敗する例もありますが、今回はうまくいったと思います。自己満足ですが…。(笑)
クロス工事が順調に進んでいます。ロフト部分のクロスも貼り終わり、玄関正面壁のポイントクロスも貼り分けが終わりました。このポイントクロスは使い方を間違えると失敗する例もありますが、今回はうまくいったと思います。自己満足ですが…。(笑)2013.01.10
2013.01.08
2012.12.25

 外部のバルコニー面に縦格子を取り付けました。木目調のアルミ格子です。白い壁に少し濃いめの木目がとってもマッチしています。又、格子の下部には黒っぽいタイルの外壁があり、3色のコントラストがきれいに組み合わさっております。ますます早く足場を外したくなってきました!(笑)
外部のバルコニー面に縦格子を取り付けました。木目調のアルミ格子です。白い壁に少し濃いめの木目がとってもマッチしています。又、格子の下部には黒っぽいタイルの外壁があり、3色のコントラストがきれいに組み合わさっております。ますます早く足場を外したくなってきました!(笑)2012.12.20

 外壁仕上げのグラナダが完了しました。ワルツというコテ模様仕上げとなっていますが、これは扇状にコテを動かして模様をつけます。(写真ではわかりつらいですが…。)
外壁仕上げのグラナダが完了しました。ワルツというコテ模様仕上げとなっていますが、これは扇状にコテを動かして模様をつけます。(写真ではわかりつらいですが…。)すごくきれいな仕上げとなっておりますので、早く足場を外して皆さんに見てもらいたいです!
2012.12.18
2012.12.13

 外壁の仕上げにかかりました。外壁の大半がグラナダ仕上げで、一部をタイル貼りにて仕上げます。タイルにはボーダー形状とキューブ形状の2種類を使用します。又、グラナダ仕上げの箇所はジョイント部分のパテ処理を行いました。
外壁の仕上げにかかりました。外壁の大半がグラナダ仕上げで、一部をタイル貼りにて仕上げます。タイルにはボーダー形状とキューブ形状の2種類を使用します。又、グラナダ仕上げの箇所はジョイント部分のパテ処理を行いました。2012.12.11
2012.12.06
2012.12.04

 外装の下地が出来上がりました。無塗装板のサイディングを貼りましたが、この上に菊水化学の「グラナダ」という仕上げをします。
外装の下地が出来上がりました。無塗装板のサイディングを貼りましたが、この上に菊水化学の「グラナダ」という仕上げをします。又、軒裏も貼り終え、防火地域対応のボードと換気口を取り付けました。換気口は小屋裏部分の1/250以上も有効換気面積のあるものを使用しています。
2012.11.29


 天井断熱部分の施工を行いました。事前に貼っておいた気密シートの上部にセルロースファイバー(ハイサーム)を厚さ300mm吹き込みます。
天井断熱部分の施工を行いました。事前に貼っておいた気密シートの上部にセルロースファイバー(ハイサーム)を厚さ300mm吹き込みます。又、表面には移動防止のトップコートをかけてあります。これで断熱工事も完了です。あとは、内装工事を進めていきます。
2012.11.27

 床を貼り始めました。オーク(楢)の無垢フローリングです。幅は12cmあります。所々に節があるので梱包を開けた時点で節のチェックをし、大きなものはクローゼットの中に使うようにしています。オークならではのきれいな木目が表れています。
床を貼り始めました。オーク(楢)の無垢フローリングです。幅は12cmあります。所々に節があるので梱包を開けた時点で節のチェックをし、大きなものはクローゼットの中に使うようにしています。オークならではのきれいな木目が表れています。2012.11.22

 外装工事が急ピッチに進んでおります。下地となる無塗装のサイディングを貼る傍ら、勝手口の庇を板金で包みました。「シャープでシンプル」をモットーにしてなるべく薄く仕上げ、存在感も薄くしました。完成が待ち遠しいです!
外装工事が急ピッチに進んでおります。下地となる無塗装のサイディングを貼る傍ら、勝手口の庇を板金で包みました。「シャープでシンプル」をモットーにしてなるべく薄く仕上げ、存在感も薄くしました。完成が待ち遠しいです!2012.11.20

 玄関サッシを取り付けました。スウェドアの木製サッシです。熱貫流率が1.53W/㎡Kと、エコハウスにぴったりの性能です。
玄関サッシを取り付けました。スウェドアの木製サッシです。熱貫流率が1.53W/㎡Kと、エコハウスにぴったりの性能です。又、軒裏部分に取り付ける物干金物の下地も取り付けました。これで洗濯物もいっぱい干せそうです!
2012.11.15

 「FPの家」の重要な機能の一つ、24時間換気設備を設置しました。今回は建物が大きいのもあり、日本住環境のルフロ400を採用しました。この機械ひとつで、約370m3/hの換気能力があります。
「FPの家」の重要な機能の一つ、24時間換気設備を設置しました。今回は建物が大きいのもあり、日本住環境のルフロ400を採用しました。この機械ひとつで、約370m3/hの換気能力があります。今回は0.5回換気で266m3/hの換気量となるので十分な能力です。ちなみにこの機械は換気量調整が約20段階あるので、0.5回換気に近い換気量を設定する事ができます。
2012.11.13

 太陽光パネルの設置が完了しました。補助金申請をしていたため工事が若干遅くなりましたが、無事設置する事が出来ました!
太陽光パネルの設置が完了しました。補助金申請をしていたため工事が若干遅くなりましたが、無事設置する事が出来ました!屋根が寄せ棟形状のため南面、東面、西面に設置した総数36枚のパネルによって、約7kwの発電能力があります。早く発電できるといいなあ〜。
2012.11.07

 外部では土台水切りを取り付け、屋根と壁の取り合い部分の熨斗水切りを取り付けました。それぞれサッシの枠や屋根瓦に合わせてカラー選択を行いましたが、どちらもきれいな仕上がりとなっております。
外部では土台水切りを取り付け、屋根と壁の取り合い部分の熨斗水切りを取り付けました。それぞれサッシの枠や屋根瓦に合わせてカラー選択を行いましたが、どちらもきれいな仕上がりとなっております。いよいよ外壁工事に突入します!
2012.11.05
2012.11.01
2012.10.30

 断熱工事も順調に進んでいます。床パネルは大引との間にコーキングにて気密処理をしました。この後、構造用合板24mmを敷き込み、ジョイント部にテープを貼って再度気密をとります。
断熱工事も順調に進んでいます。床パネルは大引との間にコーキングにて気密処理をしました。この後、構造用合板24mmを敷き込み、ジョイント部にテープを貼って再度気密をとります。屋根パネルも取り付けました。難所(笑)の屋根谷部も、パネルを加工して何とか納める事ができました。
2012.10.26

 バルコニーの防水工事を行いました。FRP防水に先立ち木下地を組みましたが、下地の合板はジョイントの位置をずらして二重に貼ります。地震時等で建物が揺れた際のひび割れ防止となります。
バルコニーの防水工事を行いました。FRP防水に先立ち木下地を組みましたが、下地の合板はジョイントの位置をずらして二重に貼ります。地震時等で建物が揺れた際のひび割れ防止となります。手摺アール部分も形が見えてきました。
2012.10.22
2012.10.10

 屋根工事を終えました。屋根材は洋風平板瓦です。一体袖瓦と同質差棟を使用した事により凹凸の少ないすっきりとした納まりになっており、きれいに仕上がりました。カラーはブラウンとしましたが、外壁との組み合わせが今から楽しみです。
屋根工事を終えました。屋根材は洋風平板瓦です。一体袖瓦と同質差棟を使用した事により凹凸の少ないすっきりとした納まりになっており、きれいに仕上がりました。カラーはブラウンとしましたが、外壁との組み合わせが今から楽しみです。2012.10.02

 建て方の続きです。2日目は屋根仕舞いです。垂木はツーバイ材を使用しその垂木の厚みを利用して通気層を確保します。
建て方の続きです。2日目は屋根仕舞いです。垂木はツーバイ材を使用しその垂木の厚みを利用して通気層を確保します。もう一枚の写真は2階の床組みの状況です。90cm角に組まれた桁や梁の上に、構造用合板24mmを貼ります。井桁に組まれた2階の床下地はとてもきれいで、僕は結構好きです。(笑)
2012.09.26

 建て方を行いました。当日は朝まで大雨で(汗)本当に作業できるか心配でしたが、天気予報を信じ(笑)何とか作業する事ができました。
建て方を行いました。当日は朝まで大雨で(汗)本当に作業できるか心配でしたが、天気予報を信じ(笑)何とか作業する事ができました。作業中も曇りましたが、雨に打たれる事なく作業できました。大きな家なので屋根仕舞いまではいきませんでしたが棟上げまでは出来、上棟式も滞りなく行う事ができました。
2012.09.21

 基礎が完成しました。きれいな仕上がりの基礎となっております。基礎屋さんは大変みたいでしたが(汗)、しっかりとした基礎となり満足しています。
基礎が完成しました。きれいな仕上がりの基礎となっております。基礎屋さんは大変みたいでしたが(汗)、しっかりとした基礎となり満足しています。引き続き、土台伏せに取り掛かりました。防腐防蟻材をしっかり塗布して、土台を取り付けていきます。
2012.09.13

 立ち上がりの型枠を組み、アンカーボルトを設置し、コンクリートを打設しました。ベタ基礎部分と同様に水セメント比を50%以下とするため高強度のコンクリートとしました。
立ち上がりの型枠を組み、アンカーボルトを設置し、コンクリートを打設しました。ベタ基礎部分と同様に水セメント比を50%以下とするため高強度のコンクリートとしました。伝票で確認すると水セメント比は49%となっています。打設時にはバイブレーターはもちろん、木づちで型枠をたたきながら打設しました。
2012.09.07

 ベタ基礎部分のコンクリートを打設しました。水セメント比を50%以下にするために、呼び強度30、スランプ15cmという生コンを設定しました。
ベタ基礎部分のコンクリートを打設しました。水セメント比を50%以下にするために、呼び強度30、スランプ15cmという生コンを設定しました。真夏には厳しい打設となりましたが、なんとか打ち終える事ができました。打設後にはシート養生と散水養生を行いました。
2012.09.03


 防湿シートを貼り、鉄筋を組みました。今回もきれいな組み上がりとなっております。
防湿シートを貼り、鉄筋を組みました。今回もきれいな組み上がりとなっております。鉄筋の種類やピッチをはじめ、定着長さ、重ね代、かぶり厚等々、どれをとっても非の打ちどころがない仕上がりとなっております。開口部補強筋もしっかり入っており、配筋検査の検査員も太鼓判を押されていました。
2012.08.28

 地盤改良が終わり基礎の丁張りをかけました。今回の基礎はGL(地盤面)設定に高低差があるため、道路側部分が深基礎になっております。高さを間違えないよう気をつけて作業します。地盤改良の高さはバッチリでした!
地盤改良が終わり基礎の丁張りをかけました。今回の基礎はGL(地盤面)設定に高低差があるため、道路側部分が深基礎になっております。高さを間違えないよう気をつけて作業します。地盤改良の高さはバッチリでした!2012.08.22

 地盤改良を行いました。事前に調査を行い、表層改良1mの改良となりました。部分的に弱い場所があり、そこは1.8mの改良を行います。
地盤改良を行いました。事前に調査を行い、表層改良1mの改良となりました。部分的に弱い場所があり、そこは1.8mの改良を行います。住宅街という事を考慮し、低粉じんタイプのセメント固化材を使用しました。テストピースも採取し、強度の確認を行います。
2012.08.17
2012.08.09

 解体工事も順調に進み、事故もなく無事に完了しました。解体中は埃がたつので高圧ジェットにて散水しながら解体していきます。隣地と隙間がなくギリギリに建っていた倉庫も、お隣さんに迷惑かけることなくきれいに解体できました。敷地が広いおかげで、最後は重機を2台使っての作業でした。
解体工事も順調に進み、事故もなく無事に完了しました。解体中は埃がたつので高圧ジェットにて散水しながら解体していきます。隣地と隙間がなくギリギリに建っていた倉庫も、お隣さんに迷惑かけることなくきれいに解体できました。敷地が広いおかげで、最後は重機を2台使っての作業でした。2012.08.03
2012.08.01